下水道本管工事のご紹介
下水道本管工事の工種は、「開削工法」と「推進工法」の2種類があります。一般的に行われているのは、開削工法と呼ばれる工法で地面を掘削し下水道管やマンホールを埋設していきます。掘削深が4.0メートルまで施工ができます。それに対して推進工法は掘削深が4.0メートル以上になり、開削工法で施工できない箇所や交通量の多い道路の横断などの道路通行の妨げをできない箇所で施工をします。推進工法は、開削工法とは異なり管路の起点及び終点に立坑と呼ばれる穴を掘りその立坑間を推進機と呼ばれる機械でモグラのように掘り進んで行きます。土質・管路延長などにより様々な種類の推進機があります。

機械掘削
掘削幅は90センチメートル程度(管径Φ200の場合、管径により異なります)。1スパン4メートル又は8メートルで施工し、掘削して埋め戻しを繰り返して工事を進めます。

管布設
人力で下水道本管を布設していきます。管種は主に硬質塩化ビニル製で、管径は150ミリメートル~200ミリメートルの物を布設します。また、掘削した際に地山の崩壊を防ぐために掘削深1.5メートル以上の箇所には軽量鋼矢板を設置します。

埋め戻し
埋め戻し管を布設した後に、再生砕石を埋め戻します。舗装後、道路が沈下しないよう、20センチメートルづつ繰り返して転圧していきます。

一般的に使用される1号マンホールは、掘削深により50センチメートル~180センチメートルのコンクリート製のブロックを組み合わせて設置します。

マンホール設置
1号マンホール設置完了状況です。

公設汚水桝設置
公設汚水枡は下水道本管と宅内排水設備をつなぐ役割をするものです。道路境界から1.0メートル以内の個人敷地に設置させていただきます。

舗装復旧
すべての本管・マンホール・公設汚水枡の施工が終了した後、舗装の復旧を行います。但し、1スパン毎埋め戻し終了後、仮舗装は行います。
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8119
ファックス番号:055-979-4593
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。







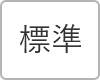
更新日:2024年07月11日