国民健康保険からの給付・支給
国民健康保険で受けられる給付について
療養の給付
国民健康保険では、療養の給付及び療養費、出産育児一時金、葬祭費等の支給を行っています。
医療機関を受診するときに、マイナ保険証を利用するか、または窓口で国民健康保険の資格確認書を提示すれば、次の負担で治療が受けられます。
| 義務教育就学前 | 医療費の2割負担 |
|---|---|
| 義務教育就学後70歳未満 | 医療費の3割負担 |
| 70歳以上75歳未満 | 医療費の2割負担 現役並み所得者については3割負担 |
現役並み所得者とは?
- 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」区分となり、自己負担割合は2割となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、同一世帯の国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する人も含めた収入合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」区分となり、自己負担割合は2割となります。 - 平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」区分となり、自己負担割合は2割となります。
入院したときの食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代を一部自己負担します。
令和7年4月より、1食あたりの標準負担額が引き上げられました。
| 一般 |
510円 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯等の人(70歳以上では低所得2) 90日まで |
240円 |
| 住民税非課税世帯等の人(70歳以上では低所得2) 91日以降(過去12ヶ月の入院日数) |
190円 |
| 70歳以上で低所得1の人 | 110円 |
(注意)低所得者1・2に該当しない小児慢性特定疾病または指定難病の人は、300円となります。
(注意)オンラインで区分が確認できない医療機関に入院する場合、住民税非課税世帯等の人は「標準負担額減額認定証」(低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。住民課国保年金係窓口にて申請してください。
(注意)国保税の滞納や所得の未申告の場合、証の発行はできませんのでご注意ください。
申請により現金・現物給付が受けられる場合があります。
子供が生まれたとき(出産育児一時金)
妊娠12週(85日)以降であれば、出産、死産、流産、早産を問わず支給されます。直接支払制度を利用した場合は、医療機関への支払いが出産育児一時金にてまかなわれます。(上限50万円(海外出産等の場合は48万8千円(令和5年))上限に満たない場合は、申請により差額が支給されます。
加入者が死亡したとき(葬祭費)
葬儀を行った方に対して5万円支給されます。
移送が困難な場合(移送費)
移動が困難な患者が入院・転院などのために、やむを得ず医師の指示のもと移送されたとき(国保が必要と認めた場合に限る)移送費(実費)が支給される場合があります。
相続人代表に関する届(世帯主が死亡した場合に届出してください。) (Wordファイル: 18.5KB)
申請により払い戻しが受けられます
次のような時、医療費を一度全額自己負担した場合には、申請により払い戻しが受けられます。
- やむを得ず、保険証を使わないで診療を受けたとき
- コルセットなどの治療装具を購入した時(医師が必要と認めた場合に限る)
- はり・きゅう・マッサージなどを受けた時(医師が必要と認めた場合に限る)
- 輸血のための生血代を負担した時
- 海外旅行中に診療を受けた時
交通事故にあったら…
交通事故など第三者から傷害を受けた時に、国保で治療を受ける場合は、必ず住民課国保年金係へ届け出をしてください。治療費は、あとで国保から加害者に請求します。必要な届け出書類は申請書ダウンロードより印刷してご利用ください。
示談が成立し、加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険で治療を受けることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。







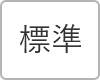
更新日:2025年04月01日