介護保険で利用できるサービスと費用
介護保険で利用できるサービス
介護保険のサービスは、「居宅サービス、介護予防サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス」に大きく分けられます。要介護の方と要支援の方とで利用できるサービスが異なります。このページでは、認定度合における利用可能なサービスの種類や、介護サービス提供事業所の検索用ホームページへの外部リンク、また、サービス利用時の負担額等についてまとめました。
要介護1から5の認定を受けた方へのサービス
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
居宅サービス
| サービスの種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。また、通院を目的とした乗降介助も利用できます。 |
| 訪問入浴介護 | 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
| 訪問看護 | 疾病などを抱えている人について、看護師が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
| 訪問リハビリテーション | 自宅での生活行為を向上させるために、理学療法士などによる訪問リハビリを行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
| 通所介護(デイサービス) | 食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
| 通所リハビリテーション (デイケア) |
食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリを日帰りで行います。 |
| 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護サービスや機能訓練を受けられます。 |
| 短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで医療、介護、機能訓練を受けられます。 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
| 福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるため以下の福祉用具を貸与します。 対象/車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ (ただし、要介護1以下の方は貸与できないものがあります。) |
| 福祉用具購入費の支給 | 日常生活を助けるため、以下の福祉用具を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に、年間10万円を上限として、購入費のうち利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額を支給します。 対象/腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分 (町に申請が必要です。) |
| 住宅改修費の支給 | 日常生活を助けるため、下記の住宅の改修を行った場合に、20万円を上限として、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額を支給します。支給を受けるためには、改修前に町から工事内容の確認を受ける必要があります。 対象/手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、和式から洋式への便器の取替え (町に申請が必要です) |
| 居宅介護支援 (介護サービス計画作成) |
介護サービスを適切に利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。 |
福祉用具購入と住宅改修については申請が必要になりますので、必ず購入・改修の前に介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
施設サービス
| 施設の種類 | 施設の内容 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所できます。日常生活上の支援や介護を受けることができます。 平成27年4月から新規入所は原則、要介護3以上の人となりました。 |
| 介護老人保健施設 | 病状が安定している方に対し、主に看護や介護、リハビリを行い、家庭への復帰を支援する施設です。 |
| 介護療養型医療施設 | 急性期の治療が終わり、長期療養を必要とする方のための医療施設です。 |
| 介護医療院 | 医学的管理のもとで長期療養を必要とする方が、医療のほか、日常生活上の介護などを受けることができます。 |
地域密着型サービス
| サービス・施設の種類 | サービス・施設の内容 |
|---|---|
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に、専門的なケアを含んだ日常生活上の支援を行います。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の希望に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。 |
| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者の方が、スタッフの支援を受けながら共同生活をするための住宅です。 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。常時介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所できます。日常生活上の支援や介護を受けることができます。 平成27年4月から新規入所は原則、要介護3以上の人となりました。 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
| 地域密着型通所介護 | 定員が18人以下の小規模な通所介護です。 |
要支援1または2の認定を受けた方へのサービス
- 介護予防サービス
- 地域密着型介護予防サービス
介護予防サービス
| サービスの種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 介護予防訪問入浴介護 | 自宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由から浴室の利用が困難な場合に限り、訪問による入浴介護が提供されます。 |
| 介護予防訪問看護 | 疾病などを抱えている人について、看護師が自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士などによる短期集中的なリハビリを行います。 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 日常生活上の支援やリハビリのほか、その人の目標に合わせた予防サービスを提供します。 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 介護福祉施設への短期入所の際に、予防を目的とした日常生活上の支援を行います。 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 介護老人保健施設への短期入所の際に、予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるため以下の福祉用具を貸与します。 対象/手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ |
| 介護予防福祉用具購入 | 日常生活を助けるため、以下の福祉用具を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に、年間10万円を上限として、購入費のうち利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額を支給します。 対象/腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分 |
| 介護予防住宅改修 | 日常生活を助けるため、下記の住宅の改修を行った場合に、20万円を上限として、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額を支給します。支給を受けるためには、改修前に町から工事内容の確認を受ける必要があります。 対象/手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、和式から洋式への便器の取替え |
福祉用具購入と住宅改修については申請が必要になりますので、必ず購入・改修の前に介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
地域密着型介護予防サービス
| サービス・施設の種類 | サービス・施設の内容 |
|---|---|
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に、専門的なケアを含んだ日常生活上の支援を行います。 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の希望に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者の方が、スタッフの支援を受けながら共同生活をするための住宅です。 (要支援1の方は利用できません) |
介護サービス提供事業所
ここから全国の各サービス事業所が検索できます。ただし、事業所の公表状況によっては、最新の情報と異なる場合もございます。
サービスを利用した時に支払う費用と各サービスにおける支払限度額について
介護保険のサービスを利用した場合、原則としてかかった費用の1割、2割、または3割が利用者負担になります。
その他に、通所サービスを利用した場合は食費、短期入所を利用した場合や施設に入所した場合は食費と居住費の負担が必要となります。
費用額は受けている介護度や利用状況によって、食費と居住費は世帯の所得や利用する施設によってそれぞれ異なります。
在宅サービスの費用
在宅サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる1ヶ月の上限額(支給限度額)が決められています。支給限度額以内での利用者負担は、サービスにかかった費用の1割、2割、または3割です。支給限度額を超えた場合は、全額自己負担となります。
| 要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合には、(1)サービス費用の1割、2割、または3割(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費のそれぞれの全額が利用者の負担となります。
短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者負担となります。
低所得者の方には負担限度額が設けられています
低所得の方の施設利用が困難とならないように、介護保険負担限度額認定申請をしてもらい認定された方は、一定額以上は保険給付されます。低所得の方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。
施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差が給付されます。
- 基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)
- 居住費:ユニット型個室2,006円、ユニット型個室的多床室1,668円、従来型個室1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、多床室377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
- 食費:1,392円
| 利用者負担段階 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 (本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者) |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合:320円) |
0円 |
| 第2段階 (本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方) |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合:420円) |
370円 |
| 第3段階(1) (本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合:820円) |
370円 |
| 第3段階(2) (本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合:820円) |
370円 |
| 利用者負担段階 | 施設サービス | 短期入所サービス |
|---|---|---|
| 第1段階 (本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者) |
300円 | 300円 |
| 第2段階 (本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方) |
390円 | 600円 |
| 第3段階(1) (本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方) |
650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) (本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方) |
1,360円 | 1,300円 |
ただし、以下2点いずれかに該当する場合は、支給対象になりません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が基準の金額を超える場合
- 第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
- 第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
- 第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円
- 第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。







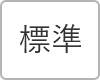
更新日:2024年03月01日