彫刻(県指定)
ここで紹介する静岡県指定有形文化財の仏像は、国指定重要文化財の阿弥陀如来及両脇侍像とともに、かんなみ仏の里美術館で保管・展示公開しています。

薬師如来坐像
薬師如来坐像(やくしにょらいざぞう)は、榧(かや)材の一木割矧造(いちぼくわりはぎづくり)です。制作年代は、堂々としながらも丸みを帯びた体つきや、円満な顔立ちなどから、平安時代中期(11世紀半ば)頃と推測されています。顔面の彫りの鋭さ、簡略ながらよくまとまった衣文(えもん)の表現、胸や腹部の厚みなど、迫力を感じさせる像容は、この時代の制作であることをうかがわせます。(本体像高110.0センチメートル)

毘沙門天立像
毘沙門天立像(びしゃもんてんりゅうぞう)は、檜(ひのき)材で、体部(たいぶ)を前後に割矧(わりは)ぐ造像技法と、動きの少ない温和な作風から、平安時代後期の中央仏師の作と考えられています。(本体像高101.5センチメートル)

十二神将立像
十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)は、東日本に現存する作例のほとんどが室町時代から江戸時代の制作で、小像が多い傾向にあります。その中で、この像は、全国的にも現存例が少ない平安時代の作品3体をはじめ、鎌倉時代、南北朝時代末頃から室町時代初期の間につくられています(うち1体は江戸時代の制作)。また、像高が1メートル前後と大きいこと、12体が揃っていることも貴重です。(本体像高91.5センチメートルから105.4センチメートル)

地蔵菩薩立像・聖観音立像
向かって左が地蔵菩薩立像(じぞうぼさつりゅうぞう)、右が聖観音立像(しょうかんのんりゅうぞう)です。両像は、丸顔の穏やかな面相(めんぞう)と彫りの浅い滑らかな起伏から、平安時代末期の作と考えられています。聖観音(しょうかんのん)と地蔵菩薩(じぞうぼさつ)を併置して祀(まつ)っている、平安時代の貴重な例です。(本体像高99.2センチメートル、93.1センチメートル)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。







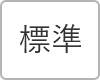
更新日:2024年03月01日