国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月(前の健康保険を脱退した月など実際に異動の生じた月)から計算します。
世帯ごとに国民健康保険加入者について算出した合計額が年税額となり、納税義務者となる世帯主に通知します。なお、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に加入者がいると、その世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)
国民健康保険税の税率(令和7年度)
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の前年の所得により算出する所得割、被保険者均等割、世帯別平等割から計算されます。
医療分、支援金分及び介護分(40歳から64歳までの人)が合算され、世帯ごとの国民健康保険税額が決められます。
令和2年度より、医療分の資産割を廃止しました。
医療分
- 所得割…(前年1月から12月の総所得金額等-430,000円)×6.62パーセント
- 均等割…1人あたり18,000円
- 平等割…1世帯につき25,000円
1から3の合計が、医療分の年税額(賦課限度額は660,000円)となります。
※医療分とは、基礎課税額のことをいいます。
支援金分
- 所得割…(前年1月から12月の総所得金額等-430,000円)×2.4パーセント
- 均等割…1人あたり7,000円
- 平等割…1世帯につき7,000円
1から3の合計が、支援金分の年税額(賦課限度額は260,000円)となります。
※支援金分とは、後期高齢者支援金等課税額のことをいいます。
介護分(40歳から64歳までの人)
- 所得割…(前年1月から12月の総所得金額等-430,000円)×2.0パーセント
- 均等割…1人あたり17,000円
1と2の合計が、介護分の年税額(賦課限度額は170,000円)となります。
※介護分とは、介護納付金課税額のことをいいます。
国民健康保険税の試算
令和7年度の国民健康保険税が、およそどれくらいの額になるか試算したい場合は、以下の試算シートをご利用ください。
注意事項 試算する前に必ずご確認ください
- 令和7年度の税率になっていますので、他の年度の試算には対応していません。
- 試算結果はあくまでも概算です。実際の賦課決定額とは異なる場合があります。
- 軽減制度等は考慮していません。
- 年度途中に加入者の人数や所得が変更になる場合等、正しい税額が試算できないことがあります。
国民健康保険税の納付(令和7年度)
国民健康保険税は、4月から翌年3月までの12か月分を普通徴収の場合年8回、特別徴収の場合年6回で納付していただきます。
年度の途中で所得の額が変更になったり、加入者の人数が変わったときなどは、後日変更になることがあります。変更の内容については納税通知書または更正(決定)通知書でお知らせします。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 7月31日 |
| 第2期 | 9月1日 |
| 第3期 | 9月30日 |
| 第4期 | 10月31日 |
| 第5期 | 12月1日 |
| 第6期 | 12月25日 |
| 第7期 | 2月2日 |
| 第8期 | 3月2日 |
- 特別徴収月(年金天引月)は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月です。
国民健康保険税の特別徴収について
国民健康保険税を年金からの天引きにより納めていただくことを、特別徴収といいます。次の4つの要件をすべて満たしている世帯が特別徴収の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険被保険者
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満
- 世帯主の公的年金の受給額が、年額18万円以上
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1を越えない
ただし、世帯主が年度途中に75歳を迎える場合は、その年度は特別徴収の対象になりません。また、年度途中に世帯状況や所得の変更等により国民健康保険税が減額になった場合には、特別徴収が中止となります。
年金天引きを希望しない場合
特別徴収の対象となる人でも、手続きをすることにより「口座振替」での納付に変更することができる場合があります。
所得が低い世帯への軽減
世帯所得(世帯主と国民健康保険加入者の前年1月から12月の総所得金額等と専従者給与支払額の合計)が一定額以下の世帯について、被保険者均等割及び世帯別平等割を軽減します。
軽減についての手続きは不要ですが、世帯主、世帯内の国民健康保険加入者及び長寿医療制度(後期高齢者医療制度)被保険者に移行した人が申告(確定申告または町民税・県民税申告)する必要があります。
| 減額割合 | 世帯主とその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等の合算額 |
|---|---|
| 7割 | 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下 |
| 5割 | 430,000円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×305,000円}+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下 |
| 2割 | 430,000円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×560,000円}+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下 |
- (注意)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。
- (注意)給与所得者等とは、世帯主、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得者(給与収入が55万円を超える人)及び公的年金等に係る所得がある人(1月1日現在で65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える人、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える人)をいいます。
軽減判定の注意事項
- 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めます。
- 令和7年1月1日現在で65歳以上の人の公的年金所得は、15万円を引いた額で判定します。
- 専従者控除があった人は、専従者控除前の所得で判定します。
- 専従者給与は専従者給与支払者の所得として計算し、専従者本人の所得には含めません。
- 譲渡所得は特別控除する前の金額で判定します。
未就学児に対する軽減
世帯に未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である人)がいる場合、その未就学児にかかる均等割が5割軽減されます。
手続きは不要です。
産前産後期間の軽減
令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。対象期間の保険税のうち、出産した人(出産予定の人)の所得割と均等割が軽減されます。
軽減期間
- 単胎の場合…出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎の場合…出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
軽減を受けるためには、原則手続きが必要です。手続きは出産予定日の6か月前からできます。住民課国保年金係(電話番号055-979-8111)にお問い合わせください。
長寿医療制度(後期高齢者)に移行する人がいる世帯の保険税の激変緩和措置
世帯に賦課される保険税の軽減(手続きは不要です)
同一の世帯に属する国民健康保険被保険者が、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)被保険者に移行することにより国保単身世帯となった場合は、平等割額が5年間半額、その後3年間は4分の1減額となります。
なお、世帯主が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行された場合にも、その家族が国民健康保険に加入している場合、その世帯の世帯主を「擬制世帯主」といい、国民健康保険税の納付や各種届出の義務を負いますので、世帯主あてに国民健康保険税の納税通知書をお送りします。
被扶養者であった人の保険税の減免(手続きが必要です)
被用者保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)被保険者に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の人(旧被扶養者)については、当面の間次の軽減措置が受けられます。
- 旧被扶養者に係る所得割が免除になります。
- 旧被扶養者に係る均等割が半額になります。国保加入日から2年間限りの減額となります。(7割・5割軽減対象者を除く)
- 国民健康保険被保険者が旧被扶養者1人の場合は、さらに平等割が半額になります。国保加入日から2年間限りの減額となります。(7割・5割軽減対象者を除く)
減免を受けるためには、手続きが必要です。住民課国保年金係(電話番号055-979-8111)にお問い合わせください。
非自発的失業者に対する軽減
65歳未満で、倒産や解雇などの非自発的失業により国民健康保険に加入した人の国民健康保険税について、前年の給与所得を30/100として算定することにより、国民健康保険税を軽減します。軽減の期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
軽減の対象となる非自発的失業者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者をいい、「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」欄の「離職理由コード(2桁のコード)」が下記の場合です。
| 離職理由コード | |
|---|---|
| 特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
| 特定理由離職者 | 23、33、34 |
軽減を受けるためには、手続きが必要です。住民課国保年金係(電話番号055-979-8111)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。







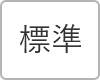
更新日:2025年04月01日